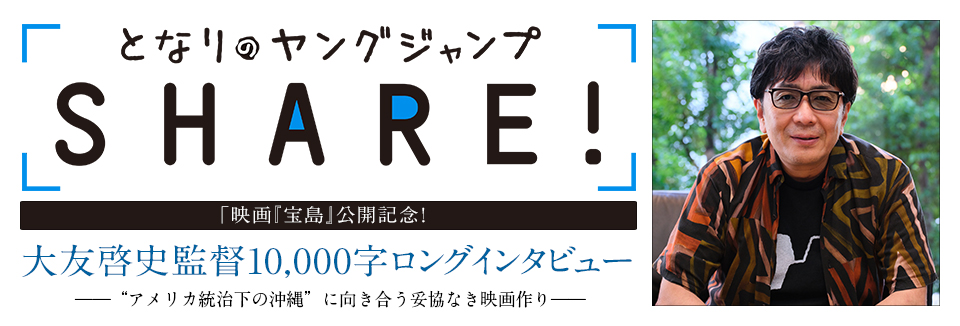

壮大なスケールで“戦後アメリカ統治下の沖縄”を描いた映画『宝島』がついに明日9月19日(金)公開! 公開を記念して、7月ヤングジャンプ誌面に掲載された大友啓史監督インタビューを“完全版”で掲載。
第160回直木賞受賞作×異才・大友啓史監督×超豪華俳優陣。
さらに、構想6年、エキストラ延べ5000人、総製作費25億円という稀に見る壮大なスケール。そして、コロナ禍での2度の撮影延期といった度重なる困難。
映画『宝島』に向き合うため、背負ったプレッシャーと覚悟を大友監督がヤンジャンで語ってくれました。演出法から複雑な題材に向かい合う覚悟、見つめ直した“映画の面白さ”についてまで。10,000字超えの熱量たっぷりロングインタビュー。
映画『宝島』と合わせてお楽しみください!
監督プロフィール
大友啓史(おおとも・けいし):
1966年岩手県生まれ。映画監督。NHKに入局し、秋田放送局に配属。97年からは2年間本場ハリウッドへ留学。その後、沖縄を舞台にした連続テレビ小説「ちゅらさん」(2001)、「ハゲタカ」等数多くの作品を演出。大河ドラマ「龍馬伝」(2010)を演出後、2011年にNHKを退局。独立後最初に取り組んだ『るろうに剣心』(2012)は、卓越したアクション表現が話題になり、シリーズ化される。その後も、『秘密 THE TOP SECRET』(2016)や『レジェンド&バタフライ』(2023)など、映画現場の最前線で作品を撮り続けている。

【原作『宝島』に惹かれた理由】
YJ 本作は真藤順丈さんによる原作がありますが、原作のどのような部分に惹かれましたか。
大友監督 まず、今の僕らがほとんど知らない、戦後の沖縄を舞台にしている点に興味を持ちました。第二次世界大戦後のアメリカ合衆国に統治されていた時代の沖縄で、沖縄の方々がどういう感情を抱いていたのか、どういう思いで生きていたのかということを、今となってはほとんどの人が知りませんからね。
YJ 特に今回は本土復帰前の複雑な時代が舞台です。
大友監督 そう。だからこそ面白いと思いました。また、原作を読んだ時、物凄い熱量に満ちた小説だと感じました。当時の過酷な時代状況の中で、登場人物たちが生きることを投げ出さずに、必死で生きている姿が魅力的だなと思って。映画でも、激動の時代に生きた登場人物たちの感情を、当時を知らない観客でもちゃんと追体験できるように描きたいと思いました。
【時代の転換点で人々が必死に生きる様子を描きたい】
YJ 大友監督は、漫画原作や小説原作の作品を多く手掛けていますが、映画化する際に題材を選ぶ基準はありますか。
大友監督 様々な経緯があるので時と場合に依ります。時には、自分の志向と違うかもしれないと思っても、新しいことに挑戦する必要もある。また、実際に興味を持って掘り下げていくと、どこかで自分の関心事と共通点が見つかったりする。なので、選ぶというよりは、様々な題材に取り組みながら、自分の世界観を大きく広げていきたいと思うタイプなのかもしれません。ただ、時代が大きく変わる転換期で、人々が必死に生きている空気感は凄く好きですね。例えば、『るろうに剣心シリーズ』でも、幕末から明治という新しい時代になって、激変する時代で生きざるを得ない人々を描いています。侍である時代は既に終わっているのに、まだ侍の魂を心の中に抱えてさすらうような人々の話ですし。
YJ 大河ドラマの「龍馬伝」とかもそうですね。本作『宝島』もその点で大友監督の過去作と共通点があるように思います。
大友監督 戦後の沖縄は、日本本土が高度経済成長で発展していくのとは対照的に、アメリカという強大な国家と琉球政府という小さい行政府が向き合っていました。激動する複雑な環境の中で多くの人たちが時代と抗いながら生きていた。その点では、過去に監督した作品にも通じるところがあると思います。
【美術の作り込みは演出に通ず】
YJ ゲート通りの風情ある様子や特飲街など、当時の沖縄を体感できるような美術にも強いこだわりを感じました。美術などを考える際はどのような点を重視していますか。
大友監督 美術の作り込みというのは、その時代を正しく表現できているか否かというだけが大事ではないんです。それ以上に、役者たちがその空間に置かれたときに、実際にその時代に生きていたかのような錯覚になれるかどうかがもっとも大切なことです。
中途半端な作り込みだと、僕自身が役者をそこに置けないと思ってしまう。役者の視界に入ってくる美術のディテールができるだけ当時の時代に近い方が、演じる上ですごく助けになると思うんですよね。
特に俳優たち自身が知らない時代を演じてもらう『宝島』のような作品では、美術は芝居のリアリティーみたいなものを引き出すための装置でもあると思います。
YJ 役者への演出自体がそこから始まっているんですね。まず、あの時代の沖縄の空気を作り込んで、役者に感じてもらうという。
大友監督 そう。演出や美術、芝居といった映像を成り立たせる要素は、線が引かれて別々に存在するのではなく、全部有機的に繋がっている。あの時代の沖縄の登場人物を演じる役者たちが、感情を引き出せるようなコンディションをスタッフ全員が同じ方向を向いて作れるかどうか。
例えば、実際にあった宮森小米軍ジェット機墜落事故を再現したシーンがありますよね。あの悲惨な場面をグリーンバックを使って合成で作っていたとしたら、もしかしたら(実際の映画内で)映っているようなヤマコの慟哭は出てこないかもしれないです。事故現場に飛び込んでいくグスクの芝居もそう。校庭に巨大な墜落の痕跡があって、みんなが子供たちを助けようとして必死でうごめいている。その状況が(役者の)眼前に広がっているかによって、彼らの心の芝居が変わってくるんじゃないかと思います。
【あの時代の沖縄を感じ取れる役者・妻夫木聡】
YJ 役者に対して細かい指示はそんなにしないのでしょうか。
大友監督 時と場合に依りますね。ただ、まずは役者本人が思うようにやってみて欲しいという思いがあります。もちろん、僕自身も思っていることや、こう動いて欲しいといったことはありますし、役者も苦しくなると何か指示が欲しくなる。でも、そこで頑張って「指示しない」ということも時には大事なことです。周囲の環境を作り込んで、そこで役者本人がどう感じるか。その主体性を引き出すことを優先しています。それはスタッフに対しても同じですね。
もちろん、もうちょっとこうして欲しいと思ったことは当然伝えていきますが、本作に集まるようなレベルの役者の場合、各々がちゃんと準備をして、僕が必要とするものを感じとってくれますからね。
YJ 本作は妻夫木聡をはじめ、広瀬すず、窪田正孝、永山瑛太といった役者が出演されて、とても豪華ですよね。例えば、主演の妻夫木聡さんはどのような役者さんでしょうか。
大友監督 沖縄の佐喜眞美術館というところに丸木夫妻iの描いた「沖縄戦の図」という絵があります。妻夫木君はそれを見て役作りしたらしいです。友人に連れられていってその絵を見たときに、「僕は今まで何も知らなかった」と感じて、言いようもない感情から泣き崩れちゃったんだって。沖縄で実施した完成披露試写会でも、妻夫木君はそのことを思い出しながら言葉が出なくなっちゃったんです、お客さんがいっぱいいる前で。
そういったことを感じられる感性の人だからこそ、難しい時代の沖縄を扱った本作の主役を務められるんだと思います。
佐喜眞美術館もそうですが、沖縄は遠いので、僕も時折何か心を鎮めたいときに、埼玉の東松山にある丸木夫妻の「原爆の図 丸木美術館」へ足を運んでいました。丸木夫妻の絵を見ると、悲しみの果てにある、人間という生き物が存在として抱えている尊厳というか、何か根源的なものを感じ取ることができます。
YJ そういった絵を見て、様々なことを一気に感じ取れる妻夫木さんのような役者じゃないと本作は務まらない。
大友監督 そうなんです。務まらない。映画は集団芸術ですし、とりわけ『宝島』のような映画は監督一人じゃ背負えないんですよね。沖縄の歴史、そして今なお生きている人たちにも繋がっている感情を背負っていくには、そのような感性を持つ役者、そして色々なことを共有してくれるスタッフがいてくれないと出来ないんです。

【感情を露わにする場面の演出】
YJ 本作は大事な場面で強い感情を表現しているのも印象的でした。特に、物語の大きな山場“コザ暴動”のシーンでは怒りを露わにする場面もありますよね。
大友監督 そこには当然怒りも含まれますが、あのシーンの場合、もっと複雑な感情がそこには表れているように思います。一言では言えないような、簡単ではない感情を必要とする場合、役者本人たちの覚悟や準備、蓄積がやはり必要です。僕は沖縄の人たちと「ちゅらさん」以来とても長く付き合っているけど、彼らはすごく優しい。沖縄の人たちが怒ったところをほとんど見たことがない。本当に優しいよ。
そんな沖縄の人たちでも、許容できる一線を越えるようなことがどんどん続いていって、我慢できず、コザ暴動でいよいよそれが爆発する。そういった場面を演出する時も、ちゃんと役者が眼前で起きていることをまぶたの裏に焼き付けられるように、一つ一つのディテールを丁寧に表現しないと、俳優の中に嘘のない感情が蓄積されていかない。だから、さっきの繰り返しになるけど、周りの環境をしっかり作っていき、彼らが感じることのできる要素を時間含めてしっかり与えていく。もちろん、それは沖縄という土地がそのまま用意してくれているところもある。けれど、何より、周りのものをちゃんと受け止める感度のある役者たちであるということ、それを切り取ることのできるスタッフであるということに尽きると思います。撮影しながら、改めて本作の俳優たちの魅力、そしてスタッフの力量を知る思いでしたね。
YJ 信頼関係ですね。
大友監督 はい。

【大勢のスタッフとの連携】
YJ 本作は(日本映画の中で)製作規模がとても大きく、時代考証や作り込みも難しいと思います。そのような場合、どこまで監督がチェックし、どのようにスタッフと連携しているのでしょうか。例えば、美術で言うと、美術監督にお任せしているのか、最終チェックみたいな形で監督がチェックするのか、どのようなコミュニケーションを取っていたのでしょうか。
大友監督 基本的には事細かく最終チェックをします。まず、脚本の中のイメージをスタッフみんなで共有して、それをベースに演出チームが作っていくのに必要な資料を集めながら美術部とコミュニケーションしてどういう美術にしていくかを探っていきます。例えば特殊飲食街をどうするか、ゲート通りの風情というのはどうするか、沖縄の家をどういう風に作っていくかとか、そういうことをスタッフ同士で詰めて、何度も画に書き起こしながら、最終的に僕がチェックしてゴーを出すという感じです。
もちろん作業が膨大なので、見れているところと見れてないところもあるんですが、基本的にはできるだけちゃんと確認したいと思います。というのも、僕も最初からすべて、辿り着く場所を知っているわけじゃないですからね。小道具とか美術とか、スタッフが作ってくれたイメージをチェックしている内に、僕自身のイメージが膨らんでいくことも多い。スタッフが僕にどんどんボールを投げてきて、僕がそれを投げ返していく中で、映画のイメージもどんどん広がっていくんですね。
YJ なるほど。お互いにボールを投げ合っていくなかで、監督自身の作品理解も深まっていく。
大友監督 ただ、例えば、沖縄の着物の柄で、どれが正しくてどれが間違っているかとかまでは、僕自身が事細かには調べる余裕がない。そこは、それぞれプロなので、その専門性に委ね、一方で僕は、スタッフのみんなが自分の仕事に誤魔化しなく、思う存分力を発揮してもらえるよう場を整えていくというか。

【難しい題材に向き合うときに問われる誠実さ】
YJ スタッフに対しても、最終判断は監督が持ちますが、基本的に自主性を大事にされるのですね。けど、自主的に動いてもらうというのは相当難しいことですよね。
大友監督 人は指示されると楽をするものですから。特に僕が言ったことは、“監督が言ったのだから=正解”という風に捉えられてしまう。僕の言うことが間違っているかもしれないという発想がなくなるのが一番怖いですね。だから、相手が手を抜いていたり、誤魔化そうとしている時には、監督の僕が気づけるようにしておかなきゃいけない。
特に、本作は一面で史実を扱っているので、スタッフも最大のケアーと努力をして、歴史や事実に誠実に向き合うという姿勢が大事でした。あの時代を生きてきた関係者の方々は今もたくさんいらっしゃるわけで、その人たちに向けても、いい加減な表現をするということは絶対してはいけなかった。しかし、人はくたびれたり、周りからのプレッシャーがあったりすると、安直な方に行ってしまいそうになる瞬間がある。そこで踏みとどまれるか否かが、実写映画をやる僕らの勝負だと思います。ただ、本作に関しては沖縄の複雑な時代を描くということで、スタッフ間でも妥協しないでちゃんとやらなきゃいけないという意識が強く共有されていたように思いますね。
YJ そのようなせめぎ合いの先に作られたのが、例えば先ほど話に出た“米軍ジェット機墜落事故”のようなシーンなのですね。
【当時の人々の必死な生きざまを描く】
YJ 本作は“戦後アメリカ統治下の沖縄”というあまり顧みられてこなかった時代を描いています。その際、例えば米軍関係者もしっかり描かれています。言ってしまえば支配者側である米軍を描く際、何か意識していたことはありますか。
大友監督 基本的に善悪二元論で描かないということですね。この物語の中には、絶対的な決定権がある立場の人は誰一人出てこなくて、誰かが決定した事柄の下で、ある意味それぞれの人間が自分の役職を全うするために一生懸命生きているんですよね。
例えば、(米軍高官の)アーヴィンにしたって、色んなことを取り持とうとしてグスクに目星をつけて近づき、アーヴィンなりのやり方で島に調和をもたらそうとしていたことは間違いない。当たり前ですが、人には色んな側面があるので、その人間性に膨らみを持たせるためには、作品内の役割だけで人を決めつけていかないということが大事な気がします。
僕らの仕事は、過去のことに対して断罪したり、糾弾したり、批判したりすることではない。あの時代の人々が、どんな環境に置かれてどういう感情を持って、どのような生き方をしているか。そして、「その生きざまを、皆さんどう思いますか」ということを物語の中で提示するのが僕らの仕事なわけです。
YJ 過去のことに関しては、ついつい現代の価値基準で判断してしまいがちですが、そういうことではないのですね。
大友監督 はい。当時はそもそも、食べていくこと・明日生きることに必死だった時代ですから。そこに道徳的な善悪とか、道義的な判断が入る余裕がなかなか生まれない。とにかく生きなきゃいけないので、ね。でも、その中でも、何か「尊厳」という哲学的な言葉が浮上してくる瞬間がある。その瞬間を浮き彫りにするのが今回の僕らの仕事でしたね。
YJ なるほど。ありがとうございます。
【捨て身の覚悟で向き合った『宝島』】
YJ これまでも重厚な作品を多く手掛けてきた大友監督ですが、実際の悲惨な史実を扱っているという点や製作中断という困難も含めて、本作は特に大変さが伺えました。
大友監督 こんなしんどいこと二度とできないと思ったくらい大変でしたね(笑)。やっぱり背負っているものがとても重かったですから。こういった題材をやるときは、「もう自分の選手生命はこれで終わりだ」というくらいに思わないと出来ませんね。覚悟を決めるというか。感覚的には大河ドラマ「龍馬伝」(2010)をやっていた時に近いかもしれません。「龍馬伝」では、会社にいながらも、それまでの大河の撮影スタイル、常識や慣習をすべて変えてやっていましたから。「龍馬伝」を観て、映像をやりたいと思ってくれるような人が出てくるようになると良いよねという話を主演の福山雅治さんと当時話していました。同じように、『宝島』も深く誰かに届くと嬉しいと思って作りました。

【“映画の面白さ”に向かい直す】
YJ とても濃いお話が続いたので少し脇道にそれて…。現在活躍中の映画監督で気になっている方はいらっしゃいますか。
大友監督 難しい質問ですが、海外の監督で、例えばディミアン・チャゼル監督iiには興味がありますね。映画産業の黄金期である1920年代ハリウッドを題材とした最新作『バビロン』 (2022)も凄く好きなんですよ。元々、『ラ・ラ・ランド』や、その前のジャズを扱った『セッション』を観て、今どきの若いフィルムメーカーというより、むしろ良い意味でオーソドックスな感性で、新しいタイプの作品を作る監督だと思っていた。そんな監督が、コロナ禍で難局に陥っていた映画の歴史を改めて見つめ直そうという作品を撮ると聞いて、『バビロン』は観る前から凄い興味があった。実際観ると、冒頭で延々とパーティーをやって、時間を含めあらゆることを消費していく。そこで、ただ無茶苦茶に消費し尽くすだけの、かつてのハリウッドの、祝祭的なパワーみたいなものを延々と見せつけてくる。その冗長さと、それゆえの豊饒とカオス感に、妙に心が躍らされたんですよね。
YJ 物語を展開するという観点で言うと、ある意味で無駄なシーンと言われるリスクもありますよね。特に、最近は“早送り視聴”が話題になっていたり、むしろそういったシーンを映画経験として楽しむことが減っている印象です。
大友監督 現代では、物語を展開するのに必須の情報以外は(鑑賞者にとって)邪魔になるという考えの方が主流になっていると思います。単純化した例を出すと、学校という社会を舞台に描くのに、学校の中にいる生徒間の葛藤はあるけど、先生の存在は極めて存在感が薄い、そういった類の作品を目にすることが増えた気がする。ドラマとして転がしていくために必要な、最低限の生徒間の関係性しか描かれていないんです。でも、普通は学生同士で何かあったら先生や校長、役所、教育委員会の大人たちといった関係者・(教室の外に広がる)社会も絡んでくる。しかし、そういった我々の周りに本来ある周縁の社会をどんどん削いで、物語を展開させるために必要な、身の回りの情報だけで描くということが増えている印象です。
それはそれで良いと思いますが、一方で、「展開」のみに還元されるのではない、映画の豊かさや面白みもやはり無視してはいけないと思います。『バビロン』の冒頭のパーティーシーンで重要視されているのは、身近な人間関係だけではなくて、ハリウッド産業全体やその外にある、社会全体の無意味な蕩尽に向かっていく空気感とか、そういうものをとても大切にしているように思います。 何かストーリー以上の「抽象」を捉えようという意思を感じて、僕はすごい面白く見たんです。物語展開だけではなくて、スクリーンで起きていることに偏執的な目線を注いで、そこのある種の豊かさとか、贅を尽くした映画作りの豊かさを見せていく映画なんですよね。
YJ 確かに、映画には“情報”を伝える以上の面白さもあるのではと思います。
大友監督 はい。ベルトルッチiiiの『1900年』(1976)とかは知っていますか。
YJ 5時間を超えるベルトルッチの野心的傑作ですね。
大友監督 あの作品はイタリアの現代史を描いているわけですよね。ベルトルッチの思想も色濃く出ていますが、そういった主義・思想を抜きにしても、イタリア現代史を五時間とか六時間の映画で描くって、そういうトライアルを、作り手としては一度はやってみたいわけです。『ゴッドファーザ―』も3部作という長さを使ってそういうのを描いている。もちろん、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』(1984)もそうです。
YJ そういった物語とは関係ないところでの驚きやディテールに見られる豊かさというのはありますよね。
大友監督 『バビロン』には、それらの作品で感じたような面白さがありました。それに、ディミアン・チャゼルのハリウッド映画に対する物凄い愛が込められていたので、高く評価されるのではないかと思っていました。しかし、実際には期待されたほど賞レースで選ばれることもなくiv 、興行的にも不振だったと言われています。コロナ禍で危機にある映画産業を描き直すという側面でも、豊かな映画経験を生み出すという側面でも、多くの挑戦をしていたあの作品が評価されなかったのは、ショックでした。
【“コザ暴動”の描き方】
YJ 確かに、賞レースでも評価されなかったのは驚きでした。今のお話を踏まえると、『宝島』は時代の流れを踏まえつつも、その中で豊かな映画体験を作ろうという意識を感じました。大きな見せ場である“コザ暴動”にも長尺をあてて、当時の時代の空気感を描こうとしているように思いました。
大友監督 コザ暴動が起きたという情報を見せるだけだったら、もっと短い時間にできると思います。つまり、物語を進めるための情報として描くなら、長い尺もエキストラも含めた周辺の人物たちも必要ない。しかし、“コザ暴動”というのはそれだけじゃないよねと。あの時代に巣くっていた言葉にならない感情や蠢く空気感。“戦後アメリカ統治下の沖縄”という時代や世界そのものを画面に取り込もうとすると、あのような描き方になる。
YJ スクリーンで観る度に新たな発見がありそうな豊かな経験でした。大友監督にとっては、『宝島』を作る経験が、ある意味で“映画の面白さとは何なのか”ということを考え直す経験になったのですね。
大友監督 何度も立ち止まり、中断の危機すらあった企画ですからね。どうしても、色々なことを考えざるを得なかったですね。
【コロナ禍での闘い】
YJ 『宝島』はコロナ禍の影響で二度撮影が延期されたと聞きました。コロナ禍を大友監督はどのように過ごされましたか。
大友監督 まず、『るろうに剣心シリーズ』の最後を飾る最終章2部作が、1年公開延期となりました。さらに、やっと公開したと思ったら、緊急事態宣言が出て大都市圏での公開が難しくなった。
YJ 大都市で上映ができないということは、興行のほとんどが飛ぶということですよね。
大友監督 はい。なぜ空気の入れ替えや場内で話さないなど、映画館側も観客も努力を続けてきた映画館がダメで、舞台など他のジャンルは許されるのかなど、行政の線引きの基準に納得いかない部分も多かったですし、十年かけて作った『るろうに剣心シリーズ』がなぜこんな目に遭うんだと、心底悔しかった。だから憲法学者に話を聞きに行ったり、都庁に行ったりしました。
その時期に、「COME BACK映画祭v」というのを全興連の会長だった佐々木さんが池袋で立ち上げて。コロナ禍でスクリーンにかからなかった映画作品を上映しようというイベントです。せっかく大金をかけて作った作品が、一度もスクリーンにかからずに終わっていくという状況があったので。
YJ 特に映画の場合は、小さな自主制作でも数千万円かかります。それだけ力を入れて制作した映画が一度も上映されてないというのは悲惨な状況ですね。
大友監督 上映館が絞られた『るろうに剣心』の場合でも、「COME BACK映画祭」で取り上げた作品の場合でも、そこで起きている声なき声や悔しさというのは、想像力を広げていくと“アメリカ統治下の沖縄”の人たちの声と相似点があるような気がするんですね。
YJ なるほど、奪われたという。
大友監督 そうそう。僕の中で、コロナ禍でのここ数年のことが全部つながっていて、そこで感じたこととかも『宝島』には吐き出されていると思います。
【若い人にまっさらな頭で観てもらいたい】
大友監督 僕はちょっと希望を持っているんです。若い方々がまっさらな頭で観たときに、どういう風にこの映画を受け止めてくれるのかなと。
YJ 先入観なしに。
大友監督 そう。妻夫木君と全国宣伝キャラバンをやっているんだけど、若い人に届くんじゃないのかなという風に希望を感じました。「あっという間でした」とか、「2時間半ないしは2時間ぐらいの感覚でした」っていうような感想も頂けて嬉しいです。難しい題材を扱ってはいますが、様々な演出上の工夫やテクニック、物語の語り口を使って、「一瞬も目をそらさせないぞ」という気持ちで作ったのでね。(取材直前の)6月初旬に、沖縄で完成披露試写会をしてきました。そうすると、皆さんの感想に僕らが泣かされるもんね。この映画で伝えたかったこと、当時の沖縄を生きた人たちの感情がストレートに届いているという感じがして。
YJ ちゃんと届いているという実感があったのですね。
大友監督 はい。「あぁ、やっぱり作ってよかったな」と思いました。
YJ 本日は貴重なお話をありがとうございました。大変長い時間語って頂き有難かったです。
大友監督 こうやって伝えていきたい作品なんですよ、真正面から。本当は観る方全員と一対一で話したいくらいです(笑)。
『宝島』あらすじ
アメリカ統治下の沖縄。そこに米軍基地から物資を奪って生活する若者たちがいた。オン(永山瑛太)は、彼らのリーダーであり、町の英雄だった。
しかし、英雄は米軍基地襲撃の夜に消える。
オンと深い関係だったグスク(妻夫木聡)・ヤマコ(広瀬すず)・レイ(窪田正孝)の幼馴染三人は、それぞれの人生を歩みながら、英雄失踪の謎を追う。
20年を経て明かされる真相。そして、アメリカ統治下の沖縄を生き抜く彼らの生き様とは――。
i広島出身の画家である丸木位里、丸木俊の夫妻。二人は原爆投下直後の広島で救援活動に従事。その後、原爆の惨状を長期間にわたり描く。さらに、広島だけでなく世界の惨状にもテーマは広がり、アウシュビッツや沖縄戦などを描いた。
ii2014年に『セッション』を監督し、当時28歳という若さでありながら、狂気的な師弟関係や音楽に伴う痛みにフォーカスした新鮮な切り口で話題に。その2年後の『ラ・ラ・ランド』も大ヒットし、ハリウッドの新進気鋭の監督として注目されている。
iiiイタリアの巨匠。詩人の父の影響を受けて、幼い頃から詩や文学に親しむ。29歳の若さでファシズムに突き進む青年を流麗な映像で描いた『暗殺の森』(1970)を監督。その後、『1900年』(1976)、最後の皇帝・溥儀の生涯を描く『ラストエンペラー』(1987)といった壮大なスペクタクルの作品を監督した。
iv例えば、アカデミー賞では「作曲賞」をはじめとした三部門にノミネートされたのみであった。
v2021年12月に開催。名作から普段目にできない掘り出し作品まで計59作品が池袋にて上映された。大友監督作品では、「るろうに剣心 最終章 The Final」の上映が行われた。